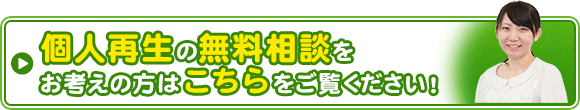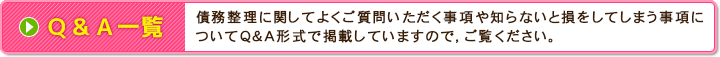「個人再生」に関するお役立ち情報
変動金利上昇で住宅ローン返済が難しい場合の対応
1 住宅ローン以外の債務を減らして抵当権の実行を防ぐ
変動金利が上昇してしまうと、住宅ローンの支払金額も増えることがあります。
場合によっては、住宅ローン支払額の増額分が家計に影響を及ぼしてしまう可能性もあります。
特に、住宅ローンのほかにも借り入れがあり、返済をしている場合には注意が必要です。
住宅ローン返済額が増えてしまったことによって、他の債務の返済ができなくなってしまうことがあるためです。
住宅ローンを含めた債務の返済が難しくなった場合の対応方法として、個人再生が挙げられます。
個人再生によって、自宅の抵当権実行を回避し、かつ住宅ローン以外の他の債務を減らすことで、住宅ローンの支払いを続けられるようにできることがあります。
以下、住宅ローンと個人再生の関係と、持ち家がある場合の返済額への影響について説明します。
2 住宅ローンと個人再生の関係
個人再生は、債務総額を大幅に減らせる可能性がある手続きですが、すべての債権者を対象としますので、住宅ローンの借入先となっている金融機関等も対象となります。
個人再生を弁護士に依頼した場合、まずは弁護士からすべての債権者に対して、受任通知という書類が送付されます。
住宅ローン会社が個人再生に関する受任通知を受け取ると、本来的には抵当権が実行されることになります。
しかし、個人再生には、住宅ローンだけは従前どおり支払い、他の債務を減額するという制度(住宅資金特別条項)が設けられています。
住宅資金特別条項を利用する場合、その旨を受任通知に記載して住宅ローン会社に送付することで、通常は一旦抵当権の実行は保留されます。
その後、裁判所に個人再生の申立てを行う際、住宅資金特別条項を利用する旨の申立てを行います。
個人再生手続きが開始されると、履行テスト、清算価値の計算、再生計画案の提出、債権者に対する意見照会などが行われます。
問題なく手続きが進められ、再生計画案が認可されると、住宅ローン以外の債務が減額されます。
再生計画が認可された後は、減額後の債務と住宅ローンの返済を行っていきます。
3 持ち家がある場合の返済額への影響
個人再生は、債務を大幅に減らせる可能性がある手続きですが、保有している財産の価値が高いと、あまり債務が減らないこともあります。
なぜなら、個人再生には、法律で定められた最低弁済額と、債務者の方が保有している財産の評価額のいずれか高い方を返済しなければならないという原則(清算価値保障原則)が存在するためです。
特にアンダーローン(自宅の評価額よりも、住宅ローンの残高が低い状態)である場合、その差額が清算価値に計上されることになります。
差額が大きい場合、清算価値保障原則によって、個人再生後の返済額も大きくなります。
個人再生を行っても、毎月の支払いが楽にならないということになりかねません。
個人再生を行う前に、詳細な見通しを確認することが大切です。